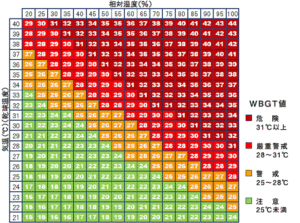人生100年の生き方
2023年8月14日
こんにちは、医務室です。毎日、毎日、暑い日(酷暑)が続いていますが、皆様お変わりありませんか?新聞で面白いテーマをみつけましたので記載します。
※心と体をスッと軽くする人生100年時代の生き方作法について
①「必要ないもの」を忘れると「本当に必要な物」がみつかる
② ネガティブな感情を忘れて自分を大切にしてあげる
③「誰かの意見」はいつだって無責任、きちんと距離を置く
④ 嫌われてしまったならさらりと離れる「身軽さ」を
⑤「私さえ我慢すれば」悲劇のヒロイン妄想は誰も幸せにしない
⑥「完璧さ」を忘れれば時間と心にゆとりが生まれる
⑦ よかった過去すら忘れて新しい自分を楽しむ
異常気象や嫌な事件、物の値上がりと暗いニュースが多い昨今、 心を軽くしてみませんか
追伸:納涼祭にて医務室で作成した花火です