支援員です。
衣替えの季節になり、八田荘のご老人も、装いに変化が出始めています。
今回は、この衣替えについて少し考察したいと思います。
明確な四季の変化があり、その季節感を大事にする日本には、古来、夏服・冬服に替える「衣替え」の習慣がありました。
古くは、平安時代の宮中行事にまでさかのぼりますが、庶民に一般化するのは、江戸時代に武家社会が成立し、そこで習慣化したものが、一般庶民に広がって行きました。
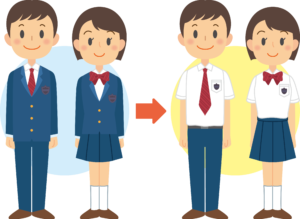 しかし、現在では、ファッションも多様になり、学校や職場生活を除くプライベートでは、「衣替え」の移行も個人のレベルで行われる為、明確な変化がなかなか分かりにくくなって来ています。
しかし、現在では、ファッションも多様になり、学校や職場生活を除くプライベートでは、「衣替え」の移行も個人のレベルで行われる為、明確な変化がなかなか分かりにくくなって来ています。
本来、衣替えとは、10月1日を目安に夏服から冬服へ、6月1日を目安に冬服から夏服へ変わる習慣です。四季がはっきりしていない国はもとより、ある程度四季の区別がある国においても、このような明確な「衣替え」の習慣がある国は、あまり見受けられません。
それでは、何故、日本においてこのような習慣が出来たのか? その背景には日本ならではの感性があります。
 その時の装いを表す為に、「秋らしい」「春っぽい」「暑苦しい」「寒々しい」等その時期に関係させた言葉が日本には沢山あり、衣替えを通して季節感を養ってきました。つまり、そこには日本の感性が息づいており、日本人が持っている美的感覚と共に、着ている服が周りの人に与える影響も考慮しながら暮らしてきたのです。
その時の装いを表す為に、「秋らしい」「春っぽい」「暑苦しい」「寒々しい」等その時期に関係させた言葉が日本には沢山あり、衣替えを通して季節感を養ってきました。つまり、そこには日本の感性が息づいており、日本人が持っている美的感覚と共に、着ている服が周りの人に与える影響も考慮しながら暮らしてきたのです。
衣替えには、日本人が育んできた季節感や文化があるのです。
戦後、欧米的なものが、生活のあらゆるレベルに流入し、利便化した半面、日本の大切な伝統の心が徐々に希薄になりつつあります。皆さんも、この衣替えの時期にあたって、個々人のレベルで、自分の興味のある日本の伝統文化を再考してみてはどうでしょうか?








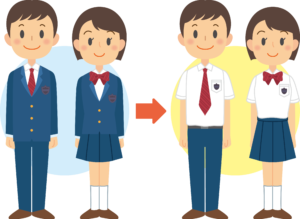 しかし、現在では、ファッションも多様になり、学校や職場生活を除くプライベートでは、「衣替え」の移行も個人のレベルで行われる為、明確な変化がなかなか分かりにくくなって来ています。
しかし、現在では、ファッションも多様になり、学校や職場生活を除くプライベートでは、「衣替え」の移行も個人のレベルで行われる為、明確な変化がなかなか分かりにくくなって来ています。 その時の装いを表す為に、「秋らしい」「春っぽい」「暑苦しい」「寒々しい」等その時期に関係させた言葉が日本には沢山あり、衣替えを通して季節感を養ってきました。つまり、そこには日本の感性が息づいており、日本人が持っている美的感覚と共に、着ている服が周りの人に与える影響も考慮しながら暮らしてきたのです。
その時の装いを表す為に、「秋らしい」「春っぽい」「暑苦しい」「寒々しい」等その時期に関係させた言葉が日本には沢山あり、衣替えを通して季節感を養ってきました。つまり、そこには日本の感性が息づいており、日本人が持っている美的感覚と共に、着ている服が周りの人に与える影響も考慮しながら暮らしてきたのです。