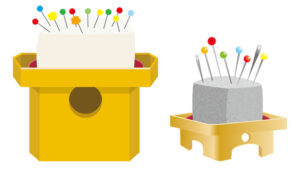啓蟄
2024年3月11日こんにちは、相談員です。

暖かな日が続くと思えば、最近は一変し冷え込みが激しくなる等、不安定な気候が続いております。
綺麗に咲いていた中庭の木蓮も、連日の雨で俯いてしまいました。
そんな最中ではございますが、3月5日は啓蟄(けいちつ)の始まりでした。
「啓」は開く、「蟄」は虫等が土中に隠れ閉じこもる意味で、合わせる事で、冬ごもりをしていた虫が這い出て来る事を指します。
季節の指標である啓蟄は3月5日から、春分の日の前日である3月19日まで続きます。
八田荘でも、本日ひな人形を片付けました。
ロビーを華やかにしていた存在が失われた事で、入所者様からも惜しむ声を多く頂きました。
ひな人形分広くなったロビーには寂しさを感じますが、これから春に向けて暖かくなる事を願いつつ、新年度に向けて少しづつ気持ちを整えて行きたいと思います。





 新しい年になり元日早々から悲しい出来事があり1日も早い復興を願う最近です。皆様いかがお過ごしでしょうか!(^^)!
新しい年になり元日早々から悲しい出来事があり1日も早い復興を願う最近です。皆様いかがお過ごしでしょうか!(^^)!